波状路のコツ

更新日:2025年6月6日
波状路は、長さ9.5m、幅70㎝のコースに不等間隔で設置された9本の枕木を、立ち姿勢で通過する課題になります。また、基準タイムがされています。尚、大型二輪教習でのみ実施されます。
波状路を「できない!」という方は少ないのですが、「何しているのか良く解らない」という方は、多くいらっしゃいます。
しかし、波状路には大型二輪を安全に運転するための練習が含まれているため、練習目的を理解して高度な技術を身に着けることが大切です。
ここでは、波状路の適切な通行方法とコツを当校の指導員が解説しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
波状路とは
波状路とは、9本の不等間隔に並べられた枕木を立ち姿勢で、且つ基準タイム以上で通過する課題になります。

波状路を練習する目的は、2つあります。
1つは、高度なバランスの取り方を身に着けることです。道路の凹凸(マンホール、アスファルトの剥がれなど)、段差を通過する際は、凹凸などの衝撃を受けることにより、車体が不安定な状態となることで、転倒する可能性が高くなります。こういった、不安定な状況に素早く対応してバランスを取る技術を身に着けます。
もう1つは、クラッチの操作技術を向上させることです。大型二輪の教習では、主に750㏄の教習車を使用しますが、免許を取得すると750㏄以上のバイクを運転できるようになります。排気量が大きいバイクでクラッチの操作が雑になってしまうと、暴走などの危険性が高くなります。
波状路を練習する中で、高度なバランスの取り方と正確なクラッチの操作を身に付けましょう。
波状路のコツ
波状路をスムーズに通過するためのコツは、
- ・運転姿勢
- ・クラッチを繋ぐ時機
- ・クラッチを繋ぐ量
- ・目標の取り方
上記、4点になります。この4点を抑えることで、安定した通過が可能になります。
それでは、コツについてご説明いたします。
運転姿勢
運転姿勢のポイントは、「体の角度」「ニーグリップ」「手首」の3つになります。
体の角度
体の角度とは、立ち姿勢を取った時の体全体の角度です。
立ち姿勢を取る場合、体の角度を概ね一直線にして前方に傾けることがポイントです。立ち姿勢で腰が落ちている状態(へっぴり腰)になると、体の重心が後方になるため、体と車体の重心が離れてしまい、不安定になります。加えて、手で体重を支える(体を支える)形になるため、アクセルやクラッチの操作が難しくなります。
体重を支える場所(体を支える場所)は、教習車がNC750であれば、メットインの端になります。具体的には、立ち姿勢を取った時に、太もも付近がメットインに引っかかるので、その部分を太ももで挟み込んで、体重を掛けるようにします。NC750以外の教習車であれば、膝でタンクを締めて体重を支えるようにして、膝から上を真っ直ぐにします。
立ち姿勢は、姿勢を取る時機が重要です。姿勢を取る時機が遅れると、綺麗な姿勢を作る時間が少なくなります。姿勢を作る時機が遅れた場合、不安定な姿勢での通過を余儀なくされます。1本目の枕木から4m~5m手前で立ち姿勢を取れるようにしましょう。

体の角度を概ね一直線にすることで、体と車体の重心が近づくため安定感が増します。更に、体を前方に傾けることで車体の浮き上がりを防止できるため、安定して枕木を乗り越えることができます。
綺麗な姿勢を作るコツは「斜め上に立ち上がる」ようにすることです。スキージャンプのようなイメージで行うと、作りやすくなります。
ニーグリップ
ニーグリップは、膝でタンクを挟み込むことを指しますが、教習車がNC750の場合、立ち姿勢を取ると膝で車体を挟みにくい状態になります。この状態を解決するためには、膝ではなく「内もも」で挟み込むようにすると、体を固定することができます。

手首
手首の角度は、少し角度をつけるようにします。理由としては、手首の角度を変えずに立ち上がるとアクセルを回すのが難しくなるためです。立ち上がった際に、アクセルを回しやすく、前輪ブレーキが掛けられる程度の角度にしましょう。
角度がつきすぎると、前輪ブレーキを掛けられなくなるため危険です。加えて、アクセルを多く回しすぎてしまう可能性が高くなります。安定した操作を行えるように、手首の角度に注意しましょう。


クラッチを繋ぐ時機
波状路でハンドルが取られてしまい、真っ直ぐに通過できない方は、クラッチを繋ぐ時機が遅れている可能性が高いです。
波状路でクラッチを繋ぐ最適な時機は、枕木に前輪が当たる「手前」です。
手前でクラッチを繋いで瞬発力を(半クラッチ程度)与えて、枕木を越える時にクラッチを握るようにすると「惰力走行」で枕木を越えられるようになります。この操作を行うことで、ハンドルが取られにくいため、真っ直ぐに走行できるようになります。また、惰力走行を使用して走行することから、基準タイムをクリアしやすくなります。
クラッチを繋ぐ時機が遅れると、左右にハンドルを取られてふらついてしまう原因になります。
前輪が枕木に当たる瞬間にクラッチを繋ぐと、枕木を越える力(勢い)が不足するだけでなく、瞬発力がないため、ハンドルが取られてしまい車体が左右にふらつきます。また、エンストする要因にもなります。
例として、普通車で段差に乗り上がる場合で考えてみます。前輪を段差に当てた状態で乗り上がる場合、相当の力(瞬発力)が必要となるだけでなく、乗り上がる瞬間にハンドルが取られてしまいます。しかし、乗り上がる前にアクセルを踏んで勢いを付けると、アクセルを離した状態で乗り上がることができます。
波状路でも同様の動作をイメージしていただければと思います。
クラッチを繋ぐ量
波状路でクラッチを繋ぐ量は、半クラッチ程度で十分です(アクセルを使用することが条件)。半クラッチ以上にクラッチを繋いでしまうと、一気に勢いがついてしまうため、基準タイムをクリアすることが難しくなります。
適切な瞬発力を与えるためには、クラッチの調節が重要です。アクセル量も重要ですが、クラッチで瞬発力を調節することは、アクセル操作と同程度に重要な操作になります。細かいクラッチ操作を意識して練習してみましょう。
アクセルについて
波状路で惰力走行を使用して枕木を越えるためには、瞬発力が必要になります。アクセルを使用しない場合、クラッチだけの操作となるため、瞬発力が弱くなってしまい、惰力走行で通過することが難しくなります。また、アクセルを使用しないために、クラッチを繋ぐ量が増えてしまい、瞬発力が付きすぎることもあります。安定した通過をするためには、アクセルを使用してバイクに瞬発力を与えることが重要です。
但し、アクセル量が多くなって、半クラッチ以上に繋いでしまうと、瞬発力が付きすぎるため、一気に波状路を通過してしまう恐れがあります。安定したアクセル量と半クラッチを練習しましょう。
もし、瞬発力がつきすぎてしまった場合は、惰力走行で何本か通過しておいて、力がなくなってきた段階で、再びアクセルを使用して瞬発力を与えるようにしてみましょう。
アクセルの使用に関しては、重要な考え方があります。それは「クラッチで速度を調節する」という考え方です。アクセル量が多少ズレてしまっても、クラッチで調節することができれば、安定した状態で波状路を通過するできるようになります。最終的には、アクセル量と半クラッチを安定させることが目標です。但し、アクセル量が安定しない場合は、クラッチで調節することを意識して練習しましょう。
目標の取り方
目標の取り方とは「見る所」を指します。
波状路での目標の取り方は、「越えようとする枕木」ではなく「1本先」の枕木です。
越えようとする枕木を見てしまうと、クラッチを繋ぐ時機が遅れる原因となります。しかし、1本先の枕木を見ることで、クラッチを繋ぐ時機が解りやすくなり、時機の遅れを防止することができます。
冒頭でも述べましたが、枕木は一定の間隔で設置されておらず、不等間隔で設置されています。そのため、同じ時機にクラッチを繋いでしまうと、エンストやふらつきの原因となります。そういったことから、一本先の枕木を見ながらタイミングを取ることが重要になります。
枕木を乗り越える度に、目標を移動させることを忘れないようにしましょう。
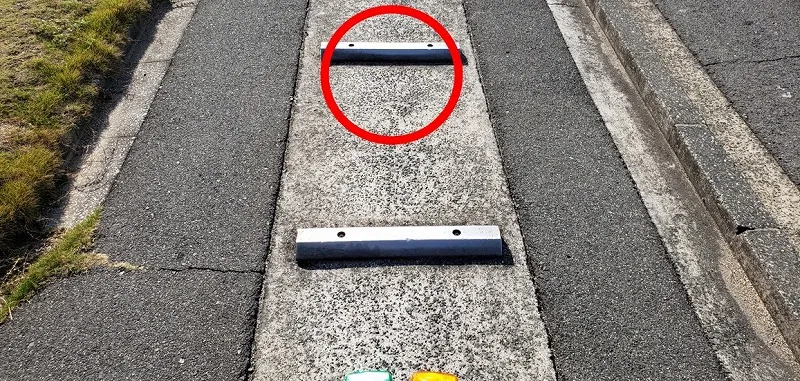
真下を見ないように注意しましょう。
動画で確認
補足
「立つこと、半クラッチで低速走行することを別々で行うことは、出来るけど同時になると難しい」と、仰られる方は少なくありません。同時が難しい場合は、立ち姿勢から練習しましょう。理想的な姿勢が取れるようになると、車体が安定するため、半クラッチの操作が行いやすくなります。後は、手首の角度などに注意してアクセル量を意識してみましょう。
最後に
波状路は、教習生の方によって「良くできている所」と「課題となっている所」が違います。まずは、ご自身で不得意と感じている部分を抽出していただいて、1つずつ改善していただきたいと思います。
勢いで通過しようとしないで、枕木を1つずつ乗り越えるイメージで練習すると上達が早くなります。姿勢、クラッチ、目標を意識して練習してみましょう。
